どうもこんばんは。肉球 (@nikuq299com) です。
最近、読みたい本が多く、まとめて購入したのですが、読書 量時間をあまり確保できておらず、積本が結構な量になってきました (読みたいと思った本があったら、とりあえず買っておくタイプです)。
基本的に紙の書籍は買っていないので、物理的な積本はないのですが、電子的積本が結構な量になってきました。
完全に思いつきなのですが、今日は世間の皆さまがどのくらい本を読んでいるのかを知りたくなったので、簡単に調べてみました。
目次
はじめに
公的機関である文化庁の統計データは平成26年度以降に調査をしていない!
まず、調査にあたってソースの取得を試みたところ、文化庁が、平成25年度「国語に関する世論調査」の結果の概要(p.10〜13) という資料を公開していました。
調査内容は4年前のものになりますが、同調査は平成26年度以降の調査結果に読書に関する内容を含めていないため、こちらを引用します。
平成26年度以降に実施している同調査結果も確認したのですが、読書に関する調査事項は含んでいませんでした。
以下、当該資料からの引用です。
調査目的:
文化庁が平成7年度から毎年実施しているもので、日本人の国語に関す意識や理解の現状について調査し、国語施策の立案に資するとと もに、国民の国語に関する興味・関心を喚起する。
調査対象: 全国 16 歳以上の男女
調査時期: 平成 26 年3月
調査方法: 一般社団法人中央調査社に委託し個別面接調査を実施
調査結果: 調査対象総数 3,473 人 有効回答数(率) 2,028 人( 58.4% )
若干サンプル数が少ないし、データの偏りもわからないですが、他に公的機関の統計資料を見つけることができなかったので、しかたなし ( どなたか、より適切な資料をご存知でしたら教えてください!) 。
世間の 読書 事情
現代人は読書に飢えているけど、時間を確保できない!?
1ヶ月に読む本の冊数について
読書量は、年を追う毎に減少傾向にあるようです。
半数が全く読まないとは、想像以上に世間から読書の機会が減っているのだなあと、少し残念に思いました。

1ヶ月で本を1冊も読まない方を年齢別で分けると、昔は読書をしていた10〜40代の年齢層において、軒並み減少傾向にありました。
50代以降の人は、もともと読書率が低かったようです。

読書 量が減っている原因
読書量が減っていいる理由は下記のとおりです。
10年前と比率がほぼ変わらない下記2点の理由は、年代別の中で読書量が多い10〜40代なのかな、と予想します。
- 仕事や勉強が忙しくて読む時間がない
- 視力などの健康上の理由
「情報機器で時間が取られる」は、5年間で11ポイント強増加えていますが、これは、恐らくスマホの使いすぎを指していると思われます。
私は、読書量の減少とスマホの普及は相関していると思っていたので、意外な結果でした。
「テレビの方が魅力的である」という理由は、5年間で3ポイント強減少しています。
こちらは、最近よく聞くテレビ離れを反映した結果なのだと思いますが、私個人の感想は、思ったよりテレビ離れしていないじゃないか、と感じました。
他の項目は特に大きな変化はないなあと思って見ていたのですが、最後の「学校での読書指導が十分でない」という理由、これは学校が悪いと言っているのでしょうか!?
この「読書量が減っている理由」は、年齢別の分析結果も合わせて見てみたかったです。

読書量を増やしたいと思うか?
男性、女性、共に50歳までは読書量を増やしたいと思う方が多いようですが、50歳以降は読書量を増やしたいと思う人が減る傾向でした。
これは、現役時代は、少しでもキャリアアップをしたくで読書時間を確保するが、それ以降は余生モードに入ってしまったので勉強は不要、という流れになっているのでしょうか。
私のまわりはこの逆で、若い人ほど読書量が少なく、年配の人ほど読書量が多い傾向でしたが、私のまわりの人間なんて数えるほどしかいないので、統計値としての正確性は引用元に叶いませんので、一般的には50代以降の読書機会が減っているのでしょう。

電子書籍を利用しているか
この調査結果からわかることは、下記2点です。
- 未だに電子書籍に抵抗を持つ人が多い (年齢が高いほど抵抗が顕著になる)
- 年齢を重ねる毎に、着実に読書する機会がなくなっている

電子書籍と紙の本・雑誌・マンガとどちらを多く利用するか
全年齢体で、圧倒的に紙媒体の書籍が支持を受けています。
私の読書スタイルは、電子書籍のみなのですが、紙媒体を利用しない人がこんなに少ないとは思ってもいませんでした。
電子書籍のみで読書をする人は、こんなにマイノリティだったんですね。

調査結果の考察
読書の減少はスマホ普及などの短期的な事象ではなく、長期的に続いている傾向のようだ!
読書の機会が減った原因
資料の調査目的に「国民の国語に関する興味・関心を喚起する」という記載があるにもかかわらず、全く言及していなかったため、勝手に考察します。
日本における読書の機会は年々、着実に減っているようです。
最初のうちは、スマホが普及したいせいかな?と思っていたのですが、どうもそうではないらしいです。
「問15 電子書籍の利用率 [年齢別] 」をよく見ると、紙・電子書籍を共に読まない人数が年齢に比例しています。
勝手な仮説ですが、これは日本人のライフスタイルから本を読むという習慣がなくなっているのでは?と思いました。
読書の機会が減る原因として思いついたのは、インターネット網の発達に伴う情報の氾濫でしたが、この調査結果を見ると、どうも腑に落ちないです。
インターネットがブロードバンドの登場で普及し始めたのが、約20年前の1998年 (平成10年) とすると、例えば、当時30歳だった人は、この調査時点で45歳になっています。
インターネットが読書の機会を奪ったのであれば、50代以降の人の読書数とは近似しなければならないと思うのですが、調査結果は完全に右肩上がりの比例関係です。
この結果を見る限り、読書時間の減少は、インターネットの登場とは関係なく、長期的なトレンドのように見えます。
読書の時間を増やすための案
データ上、読書の機会が減ることは、長期的なトレンドとに見えるわけですが、「問14 読書量を増やしたいと思うか [性・年齢別] 」を見ると、40代までの男性は7割、女性にいたっては8割の方が読書の時間を増やしたい、という回答をしています。
そこで、私は読書機会を増やすために2点の提案をします。
電子書籍でスキマ時間に読書する
「問15付 電子書籍と紙の本等の利用 [年齢別] 」を見る限り、日本は圧倒的に電子書籍より紙の書籍が流通しています (全年齢帯で約6割が紙の書籍しか利用していない)。
私も紙の書籍の良いところは理解しているつもりです。
あのアナログな操作感や、メモや付箋を貼れ、読みたい場所を一瞬で開くことができるのは紙ならではだと思います。
ただ、紙の書籍は重く大きいため、持ち運びするのに嵩張りますし、家で保管するにも大きなスペースを使うことになります。
現代の日本人は、都心回帰で十分に広い部屋に住むと、とてもコストがかかりますし、そもそも、重くて大きな本を持ち歩き、時間の隙間に読書する事も大変です。
この問題の解決案として一番最適なのは、過去の投稿で記載したペーパレス化 (電子書籍の利用) だと思います。
電子書籍は、その取扱に慣れると、紙書籍を遥かに上回る利点を享受できます。
- 保管場所を取らない
- (クラウド上に保管すれば) 紛失、破損リスクがない
- 本棚 (= タブレットに詰め込んだ電子書籍) の書籍を全て持ち歩ける
- 読んでいないページも機械検索できる
- (kindleを使っていれば) マーカーをつけた文章を一覧管理できる
出版社が電子書籍普及を主導する
電子書籍が主流にならない最大の理由はコレのきがします。
今の出版社は、自身の既得権益を守る事を最優先して、読者の事をあまり考えていないように思えます。
例えば、kindle でコミックを買うにしても、ワンピースの最新刊は、紙媒体の3ヶ月後に発売日、つまり、次の最新刊が出るまで購入できないとか、意味がわからない状態です。
恐らく、コレが原因で読者の電子書籍購入機会が少なからず減っているのではないでしょうか。
私の場合、Amazonで最新刊を見つけても、kindle版の販売は3ヶ月後で予約すらできないので、そのまま忘れて購入しない、というパターンがありました。
まとめ
このデータだけでは傾向が見えないので、文化庁さん、もっと詳細に調査してください!
読書の機会が年々確実に減っていることは分かりましたが、なぜ減っているのか?という事までは、わかりませんでした。
今回の記事は、主観が入ってしまっている部分もあるので、後日、下記についても調査を行いたいと思います。
- 小説、漫画、雑誌などの書籍ジャンル単位での読書機会
- 読書の機会が減った事による弊害
- 世界における電子書籍の普及状況
- 大手出版社のサブスクリプションサービスについて
読書は、あくまで知識の習得や疑似体験をするための手段であることは十分に理解していますが、読書に変わる手段って何があるのか思いつきませんでした。
そもそも、本好きとしては読書の機会が減っている現状は寂しい限りです。
読書の機会が減るということは、本が売れないということなので、作家を目指す人も減ってしまい、そうなると、良質な本を生み出す機会が減る事になってしまいます。
そうならないよう、素晴らしい作家が継続的に生まれるような、出版の仕組みができれば良いなと心から願います。
それでは。ごきげんよう。

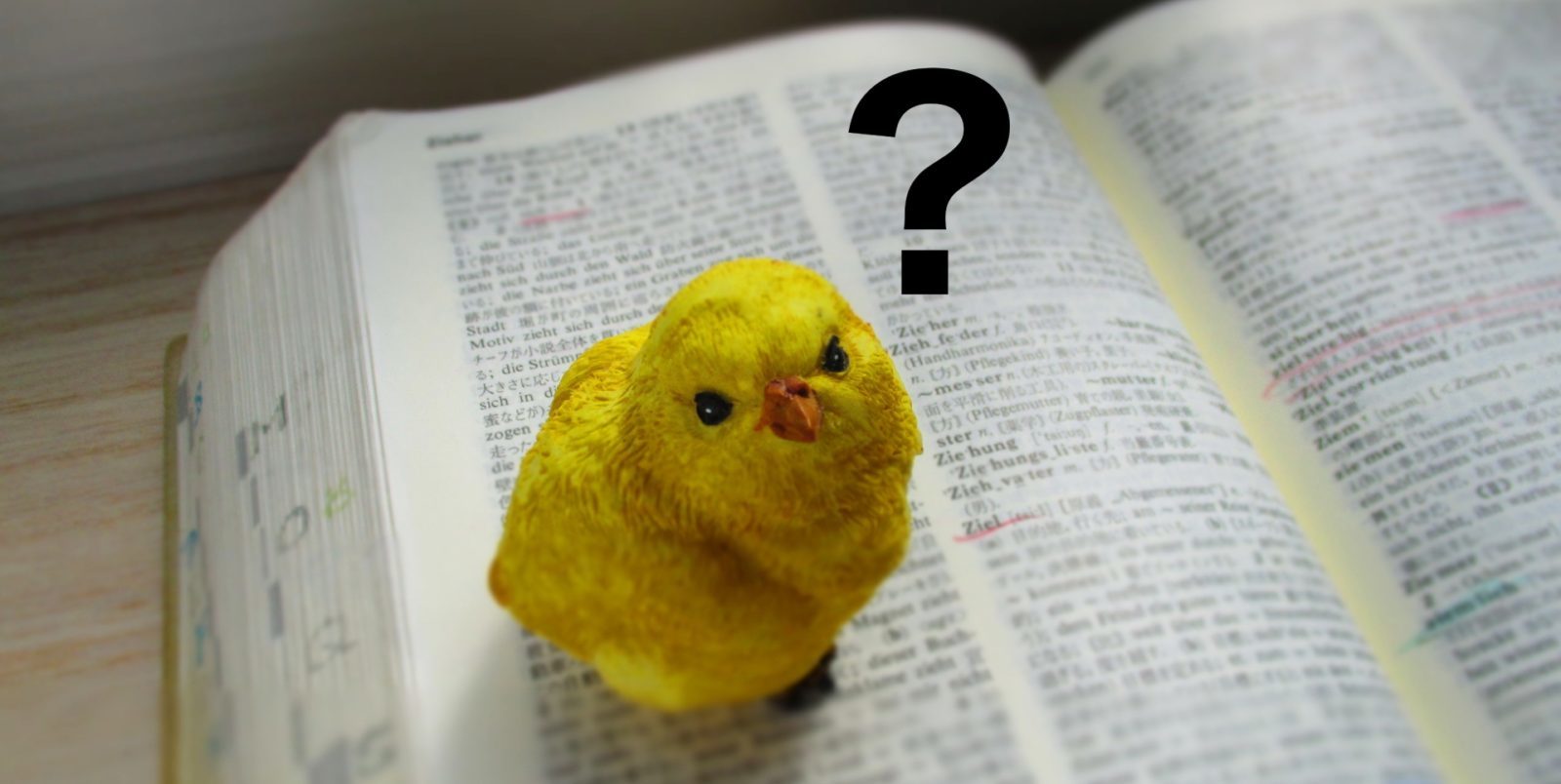

















コメントを残す